十三人の合議制とは、源頼朝を慕っていた有力御家人13人の合議制によって訴訟などを執り行った体制を指します。
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は十三人の合議制を題材にしていました。
頼朝の死後にできたこの制度はわずか1年という短い期間でしか運用されませんでしたが、その後の鎌倉幕府の権力構造に大きな影響を与えています。
この記事では、十三人の合議制が作られた目的や経緯、そして十三人の合議制に選出された御家人達を紹介しています。
十三人の合議制とは
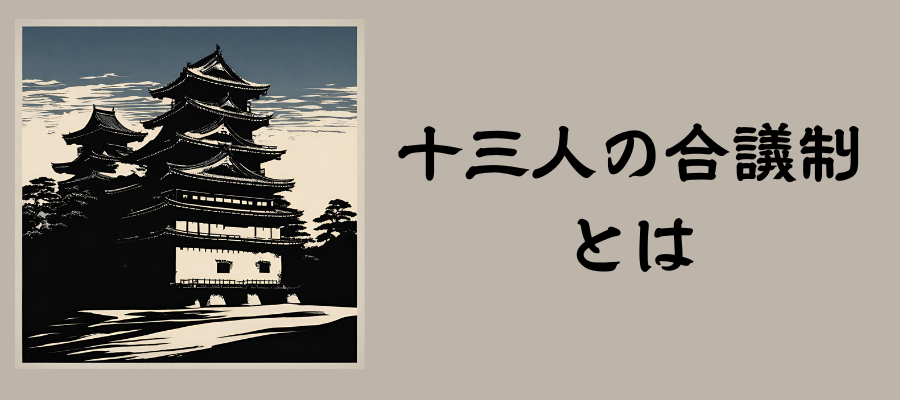
十三人の合議制は、北条氏を中心とした有力御家人によって結成されました。
当時の将軍頼家は、大江広元らの指導を受けながら訴訟の対応を行なっていました。当時所領に関わる訴訟は非常に多く、訴訟の対応は将軍の重要な責務だったのです。
しかし、ある訴訟で頼家は従来の慣例を無視した恣意的な判断を行なってしまいます。それを見た御家人は幕府の今後を不安に思い、頼家の裁断を禁止し、御家人の合議制のもと訴訟を進めることが決められました。
その後、十三人の合議制の主要人物だった梶原景時の失脚や安達盛長、三浦義澄の病死がきっかけで、十三人の合議制は解体。わずか1年でしたが、将軍の発言力を弱らせるには十分でした。
十三人の合議制が発足された背景
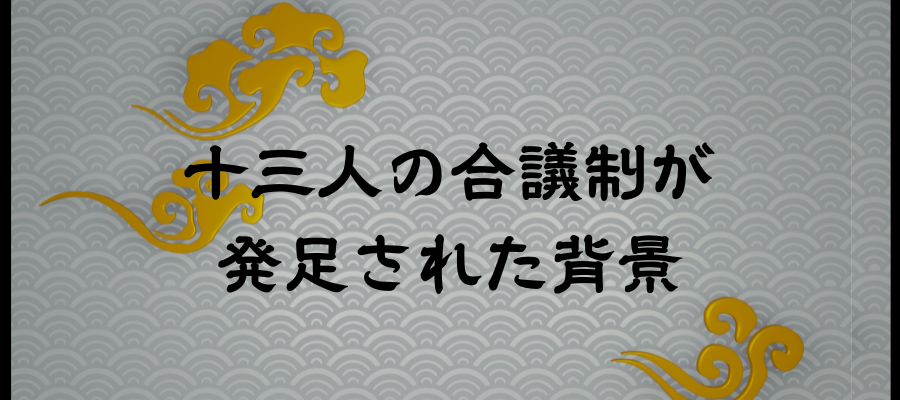
十三人の合議制が発足されたのは、源頼朝の死後でした。
頼朝が亡くなると当時18歳だった息子の源頼家が家督を継ぎます。しかし、この源頼家がかなりの曲者でした。『吾妻鏡』によると、横暴な振る舞いが目立ち、従来の慣例を無視した行いや、家臣の愛妾を略奪するといったことまで起こしています。
吾妻鏡は編纂者である北条氏の視点が強く反映されているため誇張である可能性もありますが、頼家が幕政を担うことに対し御家人達が不安を感じていたのは事実でしょう。
そこで北条政子は「十三人の合議制」を発足することを提案。合議制を導入することで実質源頼家の実権を奪うことが目的でした。
また、十三人の合議制を提案したのは、有力御家人の権力集中を防ぐ目的もあったと考えられています。
2代将軍源頼家の妻・若狭局は、十三人の合議制のメンバーでもある比企能員の娘でした。二人の間に息子が生まれたことで、比企家の発言力は強大なものになっていたのです。当時頼家自身も比企家を頼りにしています。
北条時政と政子はこの状況に危険を感じ、自分たちが立場を追われないよう、比企家だけに発言力が傾かないよう合議制を導入しました。
十三人の合議制に参加した主要人物
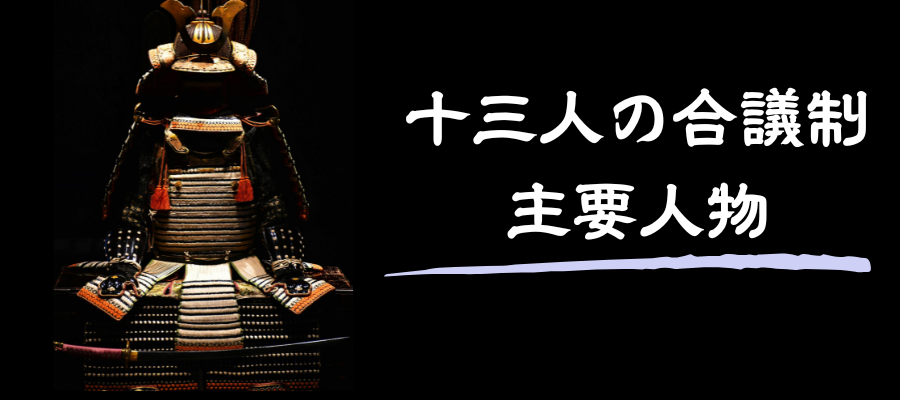
この項目では十三人の合議制に登用された人たちを紹介します。
十三人の合議制に参加していたメンバーのほとんどが平氏討伐の際源頼朝に貢献をしていた御家人達でした。
北条義時(ほうじょうよしとき)
北条義時は十三人の合議制の中心人物です。のちに2代目執権として執権政治の礎を築きます。
源頼朝が平氏討伐のため伊豆で挙兵した際は、父、兄とともに義時も参加しています。合戦での功績もあり、寝所の警護に抜擢されるなど源頼朝から篤い信頼を得ていました。また、北条政子の弟として頼朝の側近御家人に登用されます。
十三人の合議制に参加したのちは、北条時政と協力しながら他の有力御家人達を排除し、自身の権力を確立させていきました。
北条時政(ほうじょうときまさ)
北条時政は娘の政子とともに十三人の合議制を立ち上げた重要人物です。これから100年以上続く「執権政治」を始めた初代執権として知られています。
時政は対立していた比企能員を滅ぼすと、将軍頼家を失脚させ3代将軍実朝を立てます。3代将軍実朝は兄頼家の死を目の当たりにしたことで政治にはかかわらない姿勢を貫いていました。
そのため時政は「執権」という立場で政治の実権を握ることができたのです。
和田義盛(わだよしもり)
和田義盛も源頼朝の家臣であり、平氏討伐に大きく貢献したことで地位を高めました。しかし、3代将軍実朝が立った頃、北条義時との対立が激化。北条氏への反乱を企てますが、仲間だった三浦義村が裏切ったことで戦況が変わり、討ち死にました。
梶原景時(かじわらかげとき)
梶原景時は源頼朝の重臣として知られ、源平の争乱から活躍していた人物です。
十三人の合議制に入った直後、源頼家に「頼家の弟(のちの3代将軍・実朝)を将軍に立てる陰謀がある」と密告したことで、他の御家人によって幕府を追放されました。
比企能員(ひきよしかず)
比企能員は源頼家の妻の父として強い発言力を持っていました。危機感を覚えた北条時政と政子は、比企能員が頼家と組み北条氏を排除しようとしていると考えます。
その後まもなく北条氏の謀略により、比企能員は北条時政の自邸にて殺害されました。(比企能員の変)
三浦義澄(みうらよしずみ)
三浦義澄は鎌倉幕府が置かれた相模国の武将です。平氏討伐の際源頼朝に大きく貢献しました。鎌倉幕府成立後は相模国の守護を任され、義澄の甥だった和田義盛も侍所別当に任命されるなど、三浦氏は有力御家人として名を連ねました。
八田知家(はったともいえ)
八田知家は源氏への信心深く、源義朝から3代実朝の代まで4代にわたり仕えました。源頼家と北条時政が対立していた際にも八田知家は頼家側につき、時政側についていた阿野全成を頼家の命で殺害しています。
安達盛長(あだちもりなが)
安達盛長は源頼朝と深い親交がありました。源頼朝と北条政子を結ぶ仲人の役割をしたエピソードが有名です。
プライベートでも頼朝と仲の良かった盛長は、頼朝の死にショックを受け十三人の合議制が発足した直後出家をしてしまっています。
足立遠元(あだちとおもと)
足立遠元は東国武士出身者でありながら文官を務めた、文武に長けた人物でした。源頼朝から公文所(政務、財政を担当し、文書の作成を行う組織)の別当に任じられています。
安達盛長の甥だったとする説もありますが、確かなことはわかっていません。
二階堂行政(にかいどうゆきまさ)
二階堂行政は朝廷で税収の監査や管理を担う役所の下級官人でした。源頼朝に文官としての才能を見込まれ、鎌倉へと招かれる形で下り、新たに造る公文所の奉行を任されました。その後は他の役職も兼任し、幕府に大きく関わっています。
大江広元(おおえのひろもと)
大江広元は公家出身でありながら、源頼朝の家臣として活躍しています。政所別当と呼ばれる役職だった大江広元は、朝廷と幕府間の交渉を担う重要な役割を担っていました。頼朝の死後は北条時政、義時らと協調し、幕政に関わっています。
三善康信(みよしのやすのぶ)
三善康信は鎌倉幕府成立後に問注所という裁判に関わる活動をする組織の初代執事として登用されました。三善康信の母親が源頼朝を育てた乳母の姉妹だった縁から、頼朝とは以前から親交があったことが史料に残っています。
中原親能(なかはらのちかよし)
中原親能は鎌倉幕府成立後に源頼朝の側近になりました。公家出身の文官だった彼は、政所の官吏として頼朝に重用されています。
晩年は鎮西守護として九州方面の御家人の管理をしつつ、朝廷と幕府の折衷役も行なっていました。
十三人の合議制はなぜ「13人」だったのか?
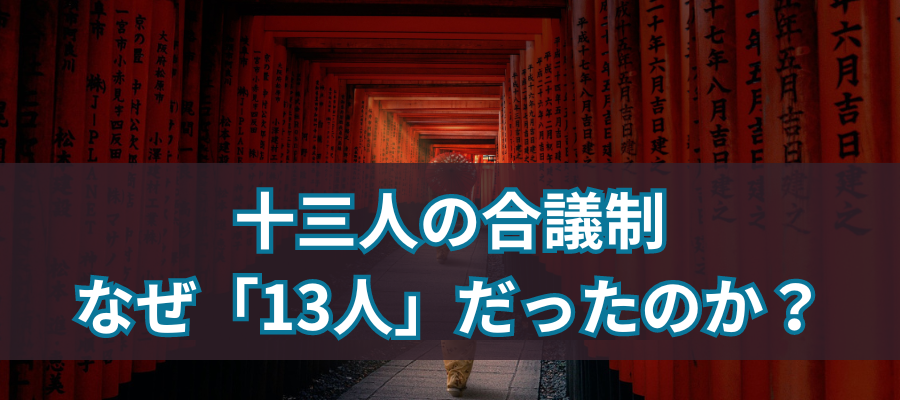
上の項目では十三人の合議制に選出された13名について紹介しましたが、そもそもなぜ上の13人が選ばれたのでしょうか。
北条政子の血縁だった時政と義時、頼家の妻・若狭局(わかさのつぼね)の父であり当時発言力を持っていた比企能員が入っていたのは当然です。
その他、幕府内で重要な役職に就いていた和田義盛(侍所別当)、梶原景時(侍所所司)、大江広元(政所別当)、三善康信(問注所執事)らは欠かすことのできない人物でした。
続いて文官として優秀で公文所の寄人だった中原親能、二階堂行政、足立遠元も選出されます。武士には文字の読み書きを苦手とする人も多かったため、文官が登用される例は多くありました。
その他の武士については、頼朝への貢献度だけでなく、北条氏と比企氏の対立が選ばれる基準になったのではないかという説が唱えられています。
地域的に北条氏と近しい関係にあった三浦義澄と頼朝と政子との結婚を取り持った安達盛長は北条派、頼家との関係が深かった八田知家は比企派として選出されたのではないでしょうか。
いずれにせよ、十三人の合議制を契機に有力御家人たちによる権力争いが起こったのは確かでした。

